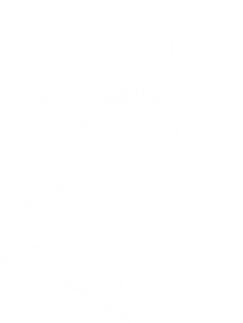ペインター

森島 巴美
Morishima Tomomi
1984年、フランス・パリ生まれ。2006年多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業後、渡独。カールスルーエ州立美術アカデミーでヘルムート・ドルナー氏(HelmutDorner)に師事し、絵画を学び、2012年卒業。現在はドイツカールスルーエを拠点に活動。作品には、建築、風景、人物などのモチーフが多い。具象的なモチーフの側面に光を帯びた色彩には、抽象絵画とのあわいが一枚の中に存在する。
WEBサイト:https://tomomimorishima.com/
◆ ◇ ◆ ◇ ◆
Q1. 「窓」という言葉から、何か思い浮かべられるイメージはありますか?
「窓」という言葉からは、やはり絵画的なイメージが強く浮かびます。制作においても、とても魅力的なモチーフだと感じています。というのも、突き詰めて考えると、キャンバスそのものがすでに「窓」だとも言えるんですよね。絵画における窓という概念は、いろいろな角度から捉えることができると思っています。
僕が小さなサイズで制作している風景のシリーズも、実はその延長線上にあります。はっきりとした壁を描かず、奥の空間を示唆するだけの構成で、いわば箱庭のような感覚の作品です。展示したこともありますが、あれも「窓」に近い発想だと思っています。
また、ヨーロッパ絵画の中には「絵の中に絵がある」という〈ピクチャー・イン・ピクチャー〉という伝統的なモチーフがあります。コレクターの部屋を描き、その中にさらに絵が描かれているような構図ですね。どこか遊び心のある、箱庭やおままごとのような感覚があって、とても魅力的な表現だと思いますし、そこには作家の主観も重なってくる。
四角いフレームというのも面白いところで、それ自体が「絵」とも「窓」とも捉えられる。四角い空間を、さらに四角い絵の中に描くことで、絵の中にもうひとつ絵をつくるようなイメージが生まれます。少し抽象的かもしれませんが、描いている側としてはとても自然な感覚なんです。
現代の画家にとっても、窓はおそらく多くの人が惹かれるモチーフだと思います。こちら側と向こう側、その境界があること、そしてそこからどこへ連れていけるか。絵画を通して、できるだけ外へ、奥へと連れていきたいと、誰もが考えているのではないでしょうか。
壁のように空間を閉じるのか、それとも奥行きを強く意識させるのか。ヨーロッパ絵画の歴史を見ても、そうした試みは数多くあります。その中で、窓という存在は、空間と存在感の両方を強く感じさせてくれる、絵画にとても近い、そしてとても面白いモチーフだと思っています。
Q2. 光や陰影、色彩のコントラストを用いる時に、何か考えていることはありますか?
光や影、コントラストについては、色彩とは少し違う役割として捉えています。僕の中では、コントラストはどちらかというと「エフェクト」に近い存在で、まず先に来るのは色彩です。
色彩は、人の感情に直接働きかけるものだと思っています。同じ「影」でも、黄色でつくるのか、青でつくるのかで、画面の印象や面白さは大きく変わるし、絵そのもののキャラクターも変わってくる。だからまずは色をどう選ぶか、どの色で世界を立ち上げるかを大切にしています。
その上で、次に考えるのがコントラストです。たとえば赤を影として使うなら、光の当たっている部分をどうするのか。少し青みを持たせるのか、もっと飛ばすのか、どこまで暗くするのか。そうやって色同士の関係性の中で、コントラストを微調整していく感覚です。
とはいえ、僕自身はあまり強くコントラストを意識して描いているわけではありません。光と影のドラマを前面に出すというよりは、色彩のニュアンスの積み重ねで画面をつくっていきたいと思っています。フェルメールのような、明確な光と影で構成された絵画には強い魅力がありますが、ああいった表現には高度な技術が必要ですし、僕のやり方とは少し違う。
できれば、光と影を「色彩だけ」で表現できたら面白いなと思っています。同じトーンでも、青みがかった茶色と、別の質感を持つ色を組み合わせることで、画面に小さなドラマを生み出す。チラチラと視線が動くような、視覚的な遊びを色彩でつくっていきたいんです。
コントラストまで強く入れ込むと、画面は一気に複雑になってしまいますし、光と影を最初にきっちり設定しないと成り立たない部分も出てきます。具象絵画を強く描く作家の多くは、明暗から入って構図や舞台を組み立てているのではないかと思います。
たとえばライプツィヒ派の作家たちのように、古典的な絵画を現代的に描き直す人たちは、人体表現もしっかりしていて、光と影から制作に入っているはずです。一方で僕は、「今回はこの色とこの色でいこう」という色彩の設定の方が先に来る。光と影は、その色彩の中から自然に立ち上がってくれればいい。そんな感覚で制作しています。
Q3. 作品のサイズやフォーマットの違いが観客に対してどのような体験を与えられるか考えていますか?
作品のサイズによって、観客に与える体験はまったく違うものになると考えていますし、描いている感覚自体も大きく変わります。
小さな作品は、人が手に取れるサイズ感ですよね。鑑賞距離も自然と近くなるので、絵肌やマチエール、キャンバスの厚みや目の粗さまで見えてくる。どうやって描かれているのか、物としての存在感がはっきり伝わるんです。壁にぽんと掛けられた小さな画面の中に、色が重なって生まれるドラマが凝縮されている感じがして、僕はこのスケールがすごく好きですね。絵画でありながら、どこかオブジェクトとして見えるところも魅力だと思っています。
一方で、大きな作品になると話は変わります。そこには最初から「舞台が立ち上がっている」ような力があって、よりイリュージョンに近い体験になる。なので、大きな絵を描くときは、あまりオブジェクトとしては考えていません。それよりも、画面の中にどんなイメージの空間を立ち上げるか、その没入感の方が重要になってきます。
サイズごとに意識をきちんと切り替えないと、作品としてまとまらなくなってしまうんです。もし大きな作品を小品と同じ感覚で「物」としてつくろうとすると、ものすごい量の絵の具が必要になってしまう。だから大きな作品の方が、意外と薄塗りになることも多いですね。そうやってスケールに応じて描き分けながら、体験の質を変えていくことを意識しています。
Q4. 今回の展示テーマと作品の接点はありますか?
今回の展示テーマとの接点として、やはり「宗教」というものは避けて通れないと感じています。正直、これはとても難しい問いですね。
僕自身、長くドイツに滞在してきましたし、教会や宗教絵画に触れる機会も多くありました。そもそも絵画というものは、歴史的に見れば教会に飾られるものとして発展してきた側面があります。そういう意味では、絵画の根本に宗教があるという感覚は、ごく自然なものだと思っています。
だから、宗教と絵画を意識的に切り離して考えようとはしていません。たとえばレンブラントやダ・ヴィンチの作品を見て、「宗教画だ」と構えて鑑賞するというよりも、まずは純粋に「美しい」と感じる。その器の中に宗教が内包されている、という捉え方に近いかもしれません。とはいえ、自分の制作において宗教をテーマとして意識的に扱っているわけではないんです。
自分では、自由な芸術のフィールドで制作しているつもりでいます。ただ、その「自由」が成立する土台そのものが、キリスト教的なバックグラウンドの上にあるとも感じています。その枠組みの中で自由に動いているだけだとしたら、結果的に、かなりキリスト教的な感覚を語っている可能性もありますよね。
考えてみれば、現代美術そのものも、キリスト教的な価値観の延長線上にあると言えると思います。一方で日本では、西洋美術を受け入れる過程で、「美術」や「芸術」という概念が輸入され、日本絵画と分けて整理されてきました。その最初の段階には、かなり複雑な事情や混乱があったとも言われています。
日本人の場合、宗教を強く意識して生きている人は少ないかもしれません。仏教なのか神道なのかと聞かれても、はっきり答えられない人が多い。でも、祭りがあり、新年に神社へ行き、鐘を鳴らす。そうした行為自体は、立派に宗教的な営みだと思います。自分では信仰している意識がなくても、海外から見れば、それは「信仰して生きている」ように映るでしょう。
だからこそ、意識していなくても、宗教的な感覚は制作の中に入り込んでくる。芸術と宗教は、どうしても切り離せないものだと、僕は思っています。

選定理由
本展示の構成を担当する中で、禁教という日本社会の状況を経て、開国と同時にキリスト教の布教に命を懸けてきた人々の営みの一端に触れることができた。
現代社会の日常に深く根付いた様式や価値観の背景には、数えきれないほど多くの人々の尽力がある。その小さなやりとりを紐解いていく中で、手紙や言葉遣いの端々から、私はどこか「美の必要性」を感じずにはいられなかった。
日々の生活に溶け込む、かすかな光のような美しさをすくい取り、それに真摯に向き合い続けている人──私にとっての現代作家とは、そのような存在である。
その直向きな姿勢は、作品そのものに光を宿し、観る者の視線を自然と引き寄せる力を生む。
それらは観覧者にとって、自身の世界を広げるための一つの「窓」となるだろう。
聖心女子大学 グローバル共生研究所/キリスト教文化研究所共催 企画展示
宗教と共生<第1期>
「カトリックは日本社会の窓だった!」
幕末の開国と明治維新に伴って、日本社会にはいくつもの「窓」が開かれ、法・社会制度や技術、学問、芸術文化などがもたらされ、人びとの交流が始まりました。本展では、その中でも一つの独特の「窓」となって、多くの人びとが行き来し、日本社会に新しい風を送り込み、また外国にも影響を与えることになった「カトリック」に焦点を合わせます。カトリックの大学である聖心女子大学のルーツにつながる歴史を多くの皆さんに知っていただきたいと思っています。
なお、本企画展は、歴史資料の展示と「窓」や「光」などのコンセプトを共有する現代アート作品とのコラボレーションによって、歴史を「体感する」試みになっています。合わせて、ご覧いただければ幸いです。
<開催期間>
2025年10月14日(火)〜2026年4月21日(火)
<会場>
聖心女子大学4号館/聖心グローバルプラザ1階BE*hive
<アクセス>
東京メトロ日比谷線「広尾駅」下車徒歩1分
<開館時間>
10:00〜17:00(日曜日・祝日休館)
<入場料>
無料
<主催>
聖心女子大学グローバル共生研究所/同キリスト教文化研究所
<協力>
聖心会